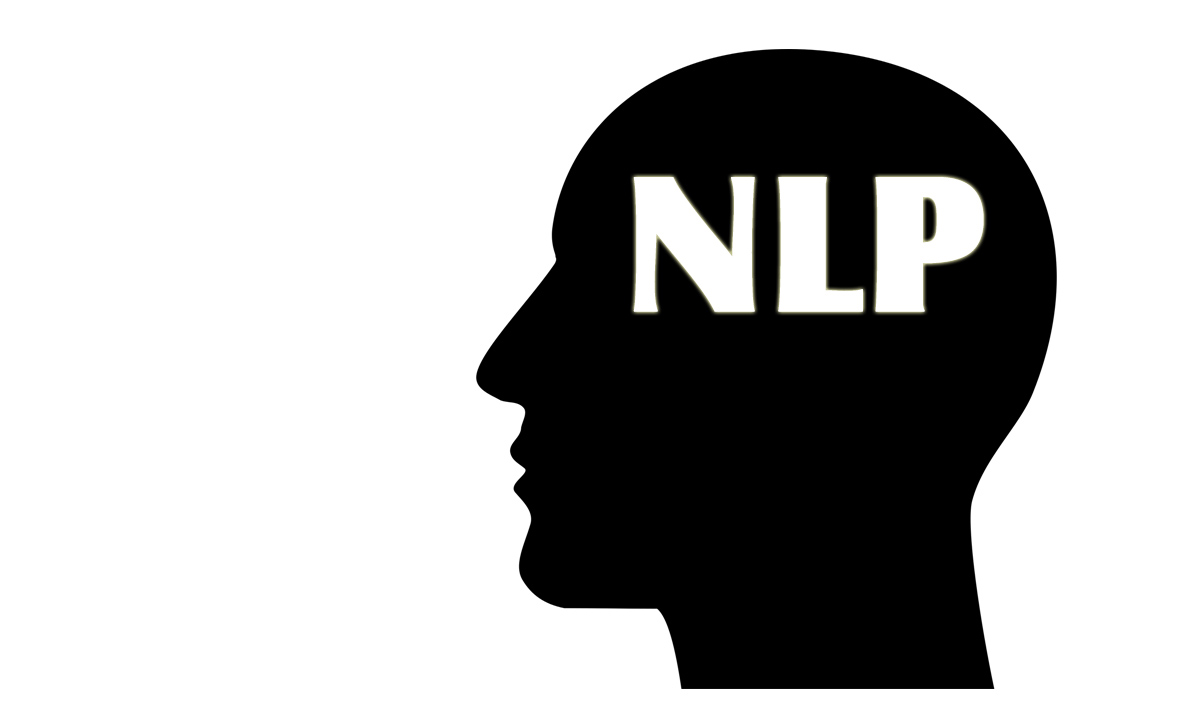NLP(神経言語プログラミング)
NLPについて
NLPは「Neuro-Linguistic Programing」の頭文字をとったもので、日本では「神経言語プログラミング」と訳されます。
人は現実世界で起こった物事を五感を通して脳内に送り、これまでの自身の経験によって形作られた考え方(地図)に照らし合わせて意思決定を行っています。
NLPは、相手と仲良くなる為に、相手がどんな考え方(地図)を通して現実世界を見ているのかを推測し、言い方や伝え方によるすれ違いを無くして、コミュニケーションをより円滑に行う為のスキルです。
元はリチャード・バンドラーとジョン・グリンダーが3人の天才セラピスト達(ミルトン・エリクソン、フリッツパールズ、バージニア・サティア)の言葉の使い方や非言語情報の使い方、無意識の使い方などを誰でも使えるように科学的に分析して体系化したものです。
レイルの講師も女性を笑顔にする為にこのコミュニケーションスキルを活用しています。
是非、あなたもあなたの大切な人を幸せにする為に使ってください。

- NLPにおける18の前提
- ①相手の世界観を尊重する
- ②行動と変化は、状況(コンテクスト)とエコロジー(環境)の観点から判断(評価)される
- ③クライアントからの抵抗は、ラポールが不足しているということ
- ④その人の行動がその人自身ではない。人を受け入れ、行動を変化させる。
- ⑤人は持てる限りのリソースを使って最善を尽くしている。
- ⑥問題、制限とは「チャンス」である。
- ⑦行動をキャリブレートする。
- ⑧地図(マップ)は領土(テリトリー)ではない。
- ⑨あなたの心/精神を管理しているのはあなた自身。よってその結果もあなたの責任である。
- ⑩心と身体は1つのシステムである。
- ⑪人は、成功や自分が望むアウトカムを達成する為に必要なリソースを全て持っている。
- ⑫すべてのプロセスは、全体性を広げるためにある。
- ⑬失敗はない、フィードバックがあるだけ。
- ⑭相手の反応があなたのコミュニケーションの成果である。
- ⑮必須多様性の法則:最も柔軟な行動をとることができる人/システムが、システムをコントロールすることができる。
- ⑯すべてのプロセスは、選択肢を広げるようにデザインされている必要がある。
- ⑰誰かにできることなら、自分にもできる。
- ⑱意識が向いているところにエネルギーは流れていく。
- 地図(MAP)
- ビリーフ(信念)
- 表象システム(VAKモデル)
NLPにおける18の前提
①相手の世界観を尊重する
現実世界において、自分の見ているものと相手の見ているものは違います。
なぜなら、考え方、好み、価値観、世界観、優先順位などが違うからです。
自分の世界観で会話をしても相手には思うように伝わりにくいですが、相手の世界観に合わせて会話をすることで、相手の言っていることが理解できるようになりますし、こちらが言うことも理解してもらえるようになります。
たとえば、子供がたまによくわからないことを話したりしますが、よくわからないからと言って反論したり無視したりしても仲良くなることはできません。
それに対し、子供の感性に合わせて会話してあげることで仲良くなることができますよね。
これは子供だけでなく、どんな相手に対しても言えます。
たとえば、男性が片想いの女友達の恋愛相談に乗る際、男性は彼氏のことを最低だと思っていても、女性はその彼氏の良い部分があるから好きなのです。
それなのに「そんなクズ、別れた方がいいよ」なんて言ってしまうと、女性に「あぁ、この人には理解してもらえないのね」と思われて嫌われてしまいます。
人によって見ているもの、見ようとしているものは違うのです。
また、人によって知識や経験は異なるので、言葉の使い方も異なります。
相手の言葉の使い方に合わせることで、仲間意識を感じさせることができ、仲良くなることができます。
その為、相手の基準に合わせることが、上手にコミュニケーションをとる秘訣なのです。
・人は現実ではなく自分の地図(マップ)を見ている
人は現実そのものではなく、自分の地図(人生経験によって培われた世界観や価値観)に照らし合わせて反応している。
その為、本当の意味で相手のことを理解する為には相手の地図を理解する必要がある。
・相手の地図を利用する
自分の地図ではなく相手の地図によってコミュニケーションを行うことで、より良い反応を得ることができる。
逆に相手の地図を無視すれば、コミュニケーションは困難である。

②行動と変化は、状況(コンテクスト)とエコロジー(環境)の観点から判断(評価)される
状況や環境によって求められる行動は変わります。
相手の行動が一見すると理解できないような行動でも、相手にとっては必要な行動なのです。
その為、相手を理解する上で、相手が何故その行動を起こしたのか?を考えることが非常に大切となってきます。
また、状況や環境によって行動や変化に対する評価は変わります。
こちらの行動がある時には有効な行動であったとしても、状況や環境が変われば通用しなくなることはよくあります。
柔軟な思考を持ち、臨機応変に対応していくことが、他人と仲良くなる上で非常に大切なことなのです。

③クライアントからの抵抗は、ラポールが不足しているということ
反抗的なクライアントはいない、あるのは柔軟性がないコミュニケーターだけ。
効果を出せるコミュニケーターは全てのコミュニケーションを受け入れ、上手に活用する。
相手に受け入れてもらえないのは、こちらの出方が合っていないということであり、コミュニケーションにおいて相手が望む形式をとってあげれば、相手はこちらを受け入れてくれるようになります。
また、相手が抵抗感を示してくるのは、こちらのことがまだ十分に信用できていないということ。
こちらが相手にとって信用に足る人物になれば、こちらの影響を受け入れてくれるようになるのです。

④その人の行動がその人自身ではない。人を受け入れ、行動を変化させる。
相手の行動から得られたイメージがそのまま相手の人格だというわけではありません。
たとえば、ジムに通っているからと言って真面目でストイックとは限りませんし、タバコを吸うからと言って性格が悪いとは限りません。
その人の本来の姿がどうであれ、その行動には肯定的意図があると考えられます。
たとえば、ジムに通うのは体型を良くしたかったり、健康になりたかったり、異性に好かれたかったりであり、タバコを吸うのは仲間からハブられない為であったり、かっこよく見えると思っていたり、ストレスを解消する為であったりです。
自分の解釈によってその人の価値を決めてしまえば、より良い人間関係やより良いチャンスを逃すことになります。
その人の肯定的意図を理解してあげて、その行動を変化させてあげることができれば、より良い関係性を築くことができるのです。
・全ての行動は肯定的意図によって起こる
人はどのような行動であっても、それによって何かを得られると感じているからそれを行う。
たとえ一見するとマイナスな行動であっても、必ずプラスな面があり、そのプラスな面を求めてそれを行っている。

⑤人は持てる限りのリソースを使って最善を尽くしている。
行動は適応する為の調整。
今、とっている行動はその人にとって最良の選択である。
すべての行動は肯定的意図によって起きている。
私たちは何かを達成する為に、つまりは肯定的意図によって行動を起こしています。
その際、自分にとって最適だと思われる方法によって行動しています。
だから、こちらが相手の行動を見て非効率だと感じるのであれば、それは相手が効率的な行動に必要な要素(リソース)をまだ持っていないからです。
それに気付かせてあげれば相手の行動を変えることができる、ということなのです。
・いつでも最善を尽くしている
人はいつでも自分がその時に最善だと思う選択を行っている。
その選択はこちらから見れば良くないものかもしれないが、相手はそれを最善の選択だと思っているので、選択を変えたいのであれば選択を増やす必要がある。
・人はいつでも完全に機能している
誰もが正しく誰もが完全であり、誰もが自分の戦略を完璧に遂行しているのだが、その戦略が効果的でない場合がある。
自分の戦略が効果的でないことに気付いた場合は、視野を広げて周りを見渡し、上手くいっている人から学ぶことで、自分の戦略をより素晴らしいものにすることができる。

⑥問題、制限とは「チャンス」である。
そこから学ぶことは、大切な意図を知ること。
問題があるからこそ人は成長でき、問題を感じるからこそ改善することができるので、問題が起こった時は成長の機会を得ることができたと前向きに捉えることが大切です。
壁に当たった時、道に行き詰った時、嘆いて立ち止まっていても何も解決しません。
また、それを無視して放置してしまうと、その先にある素晴らしい景色を見ることはできません。
「この問題には意味がある。
自分に与えられた試練であり使命。
これを解決した時、大きな新しい道が開ける。」
と前向きに捉え、
「では具体的にどう解決すればいいのか。
方法は無限にある。
この手でダメなら別の手を試すまで。
さらに効率良く解決する為にも、成功者を見習う。
同じ問題を解決している人がいるなら、誰にだって解決できる。
解決できないのは方法が違っているから。
成功者の方法を学べば、同じように成功できる。」
と考え、行動することでその問題を解決できるようになり、
新しい景色を見ることができるのです。
これは、問題があるからこそ、その問題を乗り越えることで成長することができるとうことであり、
裏を返せば、問題が無ければ成長する機会も得られないということです。
問題、制限は
・考え方をさらに前向きにし、人として大きく成長する
・新しい知識やスキル、方法を身に付け、自身の能力を成長させる
「チャンス」なのです。
・問題、制限はチャンスである

⑦行動をキャリブレートする。
その人に関する最も重要な情報は、その人の行動から得られる。
キャリブレート(キャリブレーション)とは、「測定する、調整する」という意味ですが、NLPでは「観察する」という意味で使われます。
人は必ず行動を起こしますが、行動には「目的」と「手段」があり、目的を知ることでその人の考えや欲求を知ることができ、手段を知ることでその人の経験や性格を知ることができます。
つまり、行動を観察することでその人の考え方や性格、欲求などを知ることができるのです。

⑧地図(マップ)は領土(テリトリー)ではない。
私たちが使う言葉は、それが象徴する出来事や事象そのものではない。
私たちは自身の人生経験によって形成されたフィルターを通して世界を見ています。
自分に必要ないと感じれば勝手に情報を削除し、自分にとって不都合だと感じれば勝手に情報を歪曲し、自分にとってそれが普通だと感じれば勝手に情報を一般化します。
そして、出来上がった自分なりの「まとめ」を発言として現実世界に発射します。
つまり、相手の発言は相手だけが持つ絶対的なものではなく、別の角度から見れば色々な気付きを得ることができます。
相手の言葉をそのまま捉えるのではなく、「どういうこと」を「どういうフィルターを通して発言しているか」を理解することで、「より正確な情報」と「相手の世界観」を知ることができるようになるのです。

⑨あなたの心/精神を管理しているのはあなた自身。よってその結果もあなたの責任である。
私の心/精神を管理しているのも私自身。よってその結果も私の責任である。
自分の心や行動を管理しているのは自分自身であり、その結果として今現実世界に起こっている悪いことは全て自分の責任であるということなのですが、これは裏を返せば、自分の心や行動は自分で管理することができる、つまりは好きなように変えられるということであり、その結果として現実世界で起こった良いことは全て自分のものだということです。
カナダの精神科医・心理学者であるエリック・バーンのこの有名な言葉
「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる。」
でも示されているように、
他人を変えることはできません。
NLPによって他人を誘導し、変えることはできますが、それはNLPを身に付ける=自分が変わるということです。
また、どれだけ嘆いても過去は変えられませんが、今の行動を変えれば未来は変えられます。
悲観的になったり諦めたりしても、余計辛い余生を過ごすことになるだけです。
今、行動を変えれば、未来をより素晴らしいものにすることができるのです。
ケンタッキー・フライドチキンで有名なカーネル・サンダースは、30代後半でガソリンスタンドの経営を始めるも、大恐慌のあおりを受けて倒産してしまいました。
それでもめげずに40歳でまたガソリンスタンドの経営を始め、お客さんの一言からガソリンスタンドの一角でレストランを始め、49歳でついにフライドチキンを生み出したのです。
ビジネスを成功させるのに10年近くかかり、ビジネスが成功したのも49歳と、彼は遅咲きと言えるでしょう。
ですが、前向きに頑張り続けた結果が、世界にチェーンする「ケンタッキー・フライドチキン」なのです。

⑩心と身体は1つのシステムである。
心と身体は相互に作用し、影響を与え合います。
一方に影響を与えないでもう一方を変える事はできません。
考え方が変われば身体(行動)も変わります。
行動が変われば考え方や感情も変わります。
たとえば、「彼女が欲しい」「NLPについて知りたい」と考えたからネットで検索したのであり、そう考えなければこのサイトを見ることはありませんでした。
真剣に健康が大切だと考え始めた人が、野菜をとるようになったり、ウォーキングを始めたり、タバコをやめるようになるように、考え方が変われば行動が変わるのです。
そして、テレビ番組でもたまに特集されているように、野菜をとり始めた人は本当に血が綺麗になってそれまで苦手だった野菜が好きになり、ウォーキングを始めた人は脳がさえるようになって脳トレのスコアが上昇し、タバコをやめた人はイライラすることがなくなりました。
このように、考え方が変われば身体(行動)は変わり、行動が変われば考え方や感情が変わるのです。
・心と身体は1つの有機システムである
心と身体は相互に作用していて、お互いに影響を与え合っているので、片方に影響を与えないでもう片方を変えることはできない。
考え方が変われば行動は変わり、行動が変われば考え方は変わる。

⑪人は、成功や自分が望むアウトカムを達成する為に必要なリソースを全て持っている。
リソースを持たない人はいない、リソースの足りない状態があるだけ。
リソースとは知識、経験、能力、スキル、感覚、センスなどの内部要素に加え、家族、友人、職場、インターネットなど、自分が活用できるあらゆる要素のことです。
成功や達成ができないのは、上手く活用できていないか活用の仕方を間違えているだけで、上手に活用することができれば、あらゆる目標・目的を成功、達成できます。
自分がそれに気付いていない場合は、「自分を客観視する」「試していない方法を試す」「家族に相談する」「成功者を観察しマネする」などの行動によってそれに気付くことが成功の秘訣です。
また、相手がそれに気付いていない場合は上手く気付かせてあげることで、その人を成功へと導くことができるでしょう。
・必要な資源(リソース)は全ての人がすでに持っている
多くの人がこれまでの経験によって十分な知識や能力を身に付けていて、あとはそれをどう活用するかだけである。

⑫すべてのプロセスは、全体性を広げるためにある。
全ての過程は思考(世界観)を広げ、より良い自分になる為に存在すると考えられます。

⑬失敗はない、フィードバックがあるだけ。
NLPにおける失敗は「できない。終わり」という意味ではなく「経験。別の方法」という意味であり、それによって色々なものを得ることができます。
つまり、失敗は成長や成功の為に必要な要素でもあるのです。
・失敗は存在しない

⑭相手の反応があなたのコミュニケーションの成果である。
そこから学ぶことは、大切な意図を知ること。
相手が良い反応をすればこちらのコミュニケーションの仕方が良かったのであり、相手が悪い反応をすればこちらのコミュニケーションの仕方が悪かったのです。
また、相手が自分の意図した通りに反応すれば、そのコミュニケーションの仕方は正しくて、相手が自分の意図した通りに反応しなければ、そのコミュニケーションの仕方は間違っているということです。
「こちらがどのようにコミュニケーションすれば相手はどのように感じるのか?」を把握することができれば、すべてはこちらの思い通りになるということです。
・相手の反応が自分のコミュニケーションの成果である

⑮必須多様性の法則:最も柔軟な行動をとることができる人/システムが、システムをコントロールすることができる。
うまくいかなかったら、別の方法を試してみる。
柔軟性があれば、可能性は無限に広がる。
システムとは体系や組織のことで、ここで言うシステムをもう少し掘り下げれば、「自分の行動」「生活」「機能」「相手の考え方」「人間関係」「会社組織」「ビジネス」など、秩序や規則(ルール)を持っている様々な要因を指します。
そして、その全ては柔軟に対応することで、コントロールすることができるということです。
もし、コントロールできないのなら、それは「コントロールできない存在」ではなく、こちらのアプローチ(干渉)方法が間違えているだけなので、無理だと諦めるのではなく、その方法を見つけられるように色々な方法を試すことが大切です。
・上手くいかなかったら、別の方法を試してみる
諦めてしまえばそこで終わりだが、柔軟性があれば可能性は無限に広がる。
リスクが無いのであれば、思いつく限りのあらゆる方法を試すべきである。

⑯すべてのプロセスは、選択肢を広げるようにデザインされている必要がある。
思い込みによって1つの方法しかないと考えてしまえば、行きつく先もまた1つだけになってしまいます。
柔軟な発想によって選択肢を広げることで、可能性は無限に広がります。
・何も選択しないよりも何かを選択したほうがいい
選択肢が多くなるほど自分はより自由になり、影響力を持つようになる。
選択肢を増やす為にも、いつも考えて行動することが大切である。

⑰誰かにできることなら、自分にもできる。
あとは、そのやり方を知るだけ。
同じ人間である以上、誰かができることのほぼ全ては自分にもできます。
このように言うと、「今からビルゲイツみたいに稼げるようになれるのか?」と言う人がいますが、その質問自体がそもそもの間違いです。
よく考えてみてほしいのですが、あなたが目指すべきところ、目指したい場所はそこではないはず。
誰もが誰かと全く同じになることを望んだりはしません。
人はその人なら得られる感情や快楽が欲しいだけなのです。
たとえば、ビルゲイツみたいに稼ぎたいのは「使いきれない大金が欲しい」とか「歴史に名を残したい」などの目的であって、全く同じ顔になりたいというわけではありませんよね?
そしてそれらは大抵別の方法でも手に入れられるものであり、その各プロセスにおいては必ず達成する方法があるので、「自分にはできない」と自信を無くした時は、成功者を見て「できる方法は必ずある」と事実を理解すると同時に、その方法からヒントを得ることで成功のきっかけとすることが大切だということです。
なお、その人と全く同じことができないのは、その人とは持っているリソースが違うからです。
極端なことを言えば、顔の形も身体の作りも環境も違いますよね。
けれど、手本が人間である以上、そのポテンシャルに大した差はなく、あなたが手本の持つリソースと同じようなリソースを手に入れ、手本が実践している方法と同じような方法を試すことで、似たような結果を出すことはできるのです。
・誰かにできることは自分にもできるということ
自分ができていないのは、違う方法を行っているからであり、やり方を知ればできるようになる。

⑱意識が向いているところにエネルギーは流れていく。
同時にたくさんのことをしようとすれば、エネルギーは分散されてしまい、1つのことに集中すれば、エネルギーはそこにだけ使われるようになるので効果が大きくなります。
たとえば、左手で歯磨きをしながら右手でペンまわしをしようとすると、歯磨きの速度は遅く、ペンまわしも上手くできません。
しかし、歯磨きに集中すれば的確且つ丁寧に磨けるようになり、ペンまわしに集中すれば早く正確にペンが回せるようになりますよね。
これはどんなことにも言えて、たとえば、色々な副業をしようとするとどれも中途半端になりがちですが、1つに決めて集中して行うと成果が伸びやすくなります。
同じように、もしあなたが達成したい何かがあれば、それに意識を集中させることで、エネルギーは流れ、集まり、大きな成果をもたらせてくれるのです。

※ブレッド(太字の補足)は以前に使われていた前提であり、関連する今の前提の箇所に補足として記載しています
地図(MAP)
人はこれまでの様々な自分だけの人生経験によって、自分なりの考え方、世界観、価値観を築いていて、それを基準として物事を見たり考えたりする傾向があります。
これをNLPでは地図(マップ)と言います。
たとえば、とあるレストランに食事に行った感想を聞いた場合、
Aさんは「天井にかかっているシャンデリアが見事だった」
Bさんは「店内に響く肉の焼ける音がなんとも食欲をそそります」
Cさんは「居心地が良くて料理もとても美味しかった」
などと別々のことを言ったりしますが、それは彼らが自分の価値観に基づいて判断してるからなのです。
私たちは五感から入ってきた情報を全て拾うことはできないので、無意識的に取捨選択を行っています。
たとえば、本を読んでいる時はテレビの音が耳に入らなくなったり、何かを探している時はそれに関係のないものはほとんど気にしなかったりです。
このように、人によって集める情報が異なるので、見え方も感じ方も違ってきます。
このことから、NLPでは相手と接する際に相手の見え方や受け取り方を考慮しながら接することが大切だと考えます。

ビリーフ(信念)
人生経験による思い込み
ビリーフとは、これまでの人生経験で作られた思い込みのことです。
たとえば、何か嫌なことがあった時、「成長する機会」と捉えて自分を磨けば、同じようなことがあっても乗り越えてさらに良い人生を築いていけます。
それに対し、「乗り越えることのできない壁」と捉えてその問題から目を背ければ、同じようなことがあるたびに嫌な思いをする羽目になります。
そして、それを「成長する機会」と捉えるか、「乗り越えることのできない壁」と捉えるかはあなた次第です。
ビリーフによる変化 ①外部で起こった事象 |
ビリーフによる変化の一例
①外部で起こった事象
女性に「キモい」と言われる
②五感を通して内部に入る
視覚:女性
聴覚:「キモい」と言う発言
③ビリーフによって意味付けする
A:「俺にはキモい部分があるんだな。キモいと思われる部分を直そう。」
B:「俺はキモくて女性に好かれない男なんだ。傷付くのは嫌だから女性と接するのはやめよう。」
C:「こいつ性格悪いな。俺はキモくない。こいつの目が腐っているだけだ。」
④その意味に従って対処する
A:自分を磨く
B:家に引きこもる
C:気にせずに他の女性と接する
⑤対処した結果が表れる
A:女性に好かれるようになり、素敵な女性と結婚して幸せな人生を送る
B:結婚することなく孤独な人生を過ごす
C:他の女性から「キモい」と言われ、誰にも好かれることなく人生を終える
このように、マイナスなことも意味付け(ビリーフ)を変えれば、人生を変えることができるのです。

表象システム(VAKモデル)
情報のインプットの仕方
人は「視覚」「聴覚」「嗅覚」「味覚」「触覚」「運動感覚」などによって外部情報を取り入れているのですが、NLPではこれを「視覚(Visual)」「聴覚(Auditory)」「身体感覚(Kinesthetic)」の3つの区分で考えます。
人によって優位に使っている感覚が異なるのですが、これを表象システム(VAKモデル)と言います。
地図(MAP)で紹介したレストランでの感想も、Aさんは視覚優位、Bさんは聴覚優位、Cさんは身体感覚優位に基づく感想を言っているのです。
視覚優位の傾向
視線が上に向きやすい
「~のように見える」など視覚的な表現をしやすい
早口の傾向がある、呼吸は浅め
見ためや見かけを重要視する
視覚的な言葉を多用しやすい:見る、映る、目に入る、イメージ、ビジョン、明るい、暗い、大きい、小さい、綺麗、汚い、近い、遠い、キラキラ、ピカピカ、ツルツルなど
聴覚優位の傾向
視線が左右に動きやすい
「~のように聞こえる」など聴覚的な表現をしやすい
聞くことが得意、胸で呼吸しやすい
音楽や電話が好きで雑音が苦手
聴覚的な言葉を多用しやすい:聞く、言う、耳にする、呼ぶ、叫ぶ、響く、鳴る、リズム、テンポ、音、声、静か、うるさい、ザワザワ、ドーン、パリーンなど
身体感覚優位の傾向
視線が下に向きやすい
「~のように感じる」など身体感覚的な表現をしやすい
話すテンポが遅め、お腹で呼吸しやすい
感触や居心地を重要視する
身体感覚的な言葉を多用しやすい:触る、感じる、押す、引っ張る、気持ち、感覚、リラックス、安心、興奮、緊張、味、美味しい、不味い、匂い、香り、臭い、温かい、冷たい、熱い、寒い、重い、軽い、柔らかい、固い、イライラ、ブルブル、ふわふわ、カチカチなど
コミュニケーションではVAKを使う
コミュニケーションを行う際、視覚、聴覚、身体感覚に訴えかけるような表現を使うことで、相手のイメージを膨らませ、よりワクワクしてもらいやすくなります。
非言語でのVAK
視覚
表情、視線、身振り手振りなど
聴覚
声の大きさ、声のトーン、会話のスピード、手を鳴らすなど
身体感覚
身振り手振りで感覚を表す、相手に触れるなど
言語でのVAK
視覚
感覚:見える、映る、描く、イメージ、ビジョン、大きい、小さい、速い、遅い、綺麗など
擬音:キラキラ、ピカピカ、チカチカ、つるつる、シワシワ、デコボコ、カピカピ、バラバラ、ごちゃごちゃ、ぐちゃぐちゃ、パタン、シュッと、スラッとなど
色:赤色、黄色、青色、緑色、黒色、茶色、黄金のなど
聴覚
感覚:聴こえる、音がする、響く、鳴る、叫ぶ、鳴く、吠える、さえずる、静か、うるさい、リズミカル、テンポの良いなど
擬音:ゲラゲラ、ガヤガヤ、ザワザワ、シーン、ピューピュー、ザーザー、ドーン、ゴロゴロ、パチッ、チンッ、ワンワン、ピヨピヨ、ガシャン、パリーンなど
身体感覚
感覚:感じる、触る、嬉しい、楽しい、面白い、笑う、眠い、興奮、緊張、暑い、熱い、冷たい、寒い、涼しい、硬い、柔らかい、重い、軽い、美味しい、良い匂い、臭い、元気、パワフル、ハイテンション、疲れるなど
擬音:ワクワク、ドキドキ、にこにこ、イライラ、うっとり、ふわふわ、スベスベ、ザラザラ、もちもち、もっちり、カチカチ、むにゅっ、パリパリ、ずっしり、ズキズキなど
視覚と身体感覚
メラメラ、ビュービュー、シュワシュワ、トントン、トコトコ、ドン、ドドドド、ズンズン、ドカーン、ドロドロ、のろのろ、ぷるんぷるん、ふにゃふにゃ、げっそり、ぶちゅっ、ドピュッなど
伝わりやすくする方法
視覚優位の相手
写真、絵、図、グラフなどを使う
デート先は視覚重視:オシャレ、景色が綺麗など
聴覚優位の相手
心地良いボリュームやテンポを心掛ける
デート先は聴覚重視:静か、心地良い音楽が流れている
身体感覚優位の相手
感覚や感情が伝わりやすい言葉を使う
デート先は身体感覚重視:体験できる、良い匂いがする、風が気持ち良い、温かい、ソファーの座り心地が良いなど

ラポール
信頼関係を築く
ラポールとは信頼関係のことで、こちらの言葉を受け入れてもらう為に最も重要な要素です。
元はフランス語で「収益」「関係」「報告書」などといった意味ですが、オーストリアの精神科医メスメルが、クライアントとの親和関係を表す為に用いたことがきっかけで、セラピストとクライアントとの親和関係を表す言葉として広く使われるようになりました。
なお、ラポールをフランス語で「心のかけ橋」という意味として説明しているものもありますが、ラポールは心のかけ橋と言う意味ではなく、イメージとして、セラピストとクライアントとの間に心のかけ橋をかけるような感じであると言うことなので、間違えないようにしましょう。
相手の反応は外部からの情報によって起こっているのであり、相手があなたに対して好意的なのも敵対的なのもあなたの言動が原因となっています。
つまり、こちらの与える情報を変えれば、悪い反応を良くすることができるということです。
たとえば、
弟が言うことを聞いてくれない ⇒ こちらの言い方が悪い
友達と喧嘩してしまった ⇒ こちらの接し方が悪かった
上司が厳しい ⇒ こちらの態度に問題がある
女性に好かれない ⇒ 好かれないような言動を行っている
ということになります。
では、言い方を良くするだけで相手が言うことを聞いてくれるのかと言うと、一概にそうとは限りません。
たとえば、出会ったばかりの男性が自分の紹介する保険に入ってほしいと言ってきたとして、言い方や内容が魅力的ならば了承するでしょうか?
「条件がいいのはこちらを騙そうとしているのかもしれない…」
と疑いますよね。
では、母親に「あんた、保険に入ってなくてもし何かあったらどないするん!?私と同じこの保険に入っとき!」と言ってきたらどうでしょうか?
「とりあえず入っておくか…」となりますよね。
これは相手を信用しているからであり、相手のことを信頼しているからこそ、相手の言うことを受け入れようと思うのです。
これと同じで、相手がこちらに対して疑っている状態ではあなたの言葉は刺さりません。
NLPの効果をより高める為にも、まずは相手の信頼を得ることが大切です。

マッチング
ラポールを築く為に相手と「視覚情報」、「聴覚情報」、「言語情報」などを合わせていくことが有効となりますが、これをマッチングと言います。
マッチング
視覚:姿勢や動作を合わせる ⇒ ミラーリング
聴覚:音やリズムを合わせる ⇒ ペーシング
言語:言葉を合わせる ⇒ バックトラック
ミラーリング
相手と見た感じを合わせる
人は相手と心が通じ合ってくると、無意識的に相手と似た行動をとるようになる傾向があります。
この心理を利用して相手と似た行動をとることで相手の心に入っていく方法がミラーリングです。
たとえば、
相手とまばたきを合わせる
相手の表情に合わせる
相手の喋り方に似せる
相手の姿勢や佇まいに寄せる
相手の動作に合わせて同じ動作を行う
などによって相手に同調し、
「私はあなたに(人として)好意を持っています」
「私はあなたに共感しています」
「私はあなたの仲間です」
というメッセージを相手の意識や無意識に伝えることができ、
それによって相手は少しずつ心を開いてくれやすくなります。
ただし、相手に「わざとマネをしている」と思われると逆効果になってしまいますので、相手に不快を与えないようにさりげなく行うことがポイントです。
クロスミラーリング(クロスオーバーミラーリング)
ミラーリングは相手にマネされていると思わせないくらいにさりげなく行う必要があるのですが、それには相当の訓練が必要であり、普通の人が日常で使うのにはあまり向きません。
そこで有効となるテクニックが「クロスミラーリング(クロスオーバーミラーリング)」です。
クロスミラーリングとは、相手の動作を部分的に寄せていく方法です。
たとえば、相手がお茶を飲んだら髭を触る、相手がケーキを食べたらお茶を飲む、相手が腕を組んだら足を組む、相手が足を組んだら腕を交差させるなどです。
また、会話ではテンション、トーン、スピード、リズム(テンポ)などを合わせていきます。
これによって相手にマネされていると思わせることなく一体感を作り出すことが可能になります。

ペーシング
相手のスピードに合わせる
ペーシングは相手とラポールを築く為に行います。
誰かと会話する時、相手を楽しませたくていきなりテンションを上げて接したとしても、相手に「この人は接しにくい」と思われてしまう可能性があります。
まずはペーシングによってラポールを築くことで、テンションを上げて接した時に「楽しませようとしてくれている」と理解してもらうことができるようになるのです。
人は同じ会話リズムの人だと接しやすく、会話のリズムが違うと接しにくいと感じる傾向があります。
たとえば、「この人はおっとりしすぎて自分とは合わない」などと思ったことがあると思いますが、これはその人が自分のリズムよりもゆっくりとしたリズムでコミュニケーションを行っているからです。
また逆に自分より早口だったり、感情の動きが早かったりすると、「この人はせっかちそうですぐにイライラそうだ」などと感じてしまいます。
逆にコミュニケーションのリズムが合うだけで、「この人は接しやすい」と感じて受け入れやすくなります。
これを意識的に行っていくのがペーシングです。
ペーシングの要素と手順 ①状態、テンション |
ペーシングの手順
①状態、テンション
まずは相手の状態(感情)とテンション(感情の強さ)を意識しましょう。
緊張しているのか、落ち着いているのか、興奮しているのかなど、相手がどんな状態でいるのかを見極め、その感じを合わせていきましょう。
状態を合わせることで相手の考えていることがなんとなくわかってきます。
なお、状態は最初だけでなく常に合わせ続けることが大切です。
②表情、姿勢
次に表情と姿勢を寄せていきましょう。
表情は感情を理解し共感を示す為に合わせていくので顔をマネするのではなく、表情を寄せていく感じです。
③身体の方向、手の動き、足の角度や置き方
次に身体の方向、手の動き、足の角度や置き方と少しずつ合わせていきます。
全く同じにするとマネをしていると気付かれてしまいますので、不自然でない範囲でさりげなく寄せていけば十分です。
④声のボリューム、声のトーン、発言のスピード
次に声のボリューム、声のトーン、発言のスピードを合わせていきます。
この3点は完全にマネしても気付かれないので、完全に合わせていくことが大切です。
⑤会話の内容、感情の動き、会話のテンポ
次にバックトラック(後述)を使って会話の内容を合わせていきます。
また、会話中の相手の感情の動きを読み取り、同じように感情も合わせていきます。
同時に会話のテンポも合わせることで一体感が生まれます。
⑥ワード、言い回し、捉え方、意思主張
次にワード、言い回し、意思主張を合わせていきます。
ワード:相手がマクドナルドのことをマックと言えばこちらもマック、マクドと言えばこちらもマクド
言い回し:物事の伝え方の特徴。方言やクセを合わせるわけでは無い
意思主張:相手が本当に伝えたいこと。真意。後述のスーパーバックトラックでカバーできる
⑦考え方や価値観
最後に相手の考え方、価値観、信念、道徳観などに寄せていくことで、相手はこちらを仲間と認識して好感を抱くようになります。
なお、物事の捉え方や感じ方(VAKモデル)などもここに含まれます。
呼吸は?
呼吸を合わせることで相手の感情を読み取りやすくなるのですが、呼吸を読んで合わせることはかなり難しく、上記の要素をペーシングすれば自然と呼吸が合ってくるので、コミュニケーションを極めたいと思っているわけではないのであれば呼吸を意識的にペーシングする必要はありません。

バックトラック
相手の話をオウム返しする
相手が自分の話を聞いてくれている、発言を理解してくれていると感じるほど、相手のことを信用したり好きになったりします。
バックトラック(バックトラッキング)は相手の発言を引用することで、相手にそう思わせるテクニックです。
通常の会話
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon02.jpg” name=”相手” type=”l”]昨日、スタバの新作飲んだんだ~[/voice]
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon.jpg” name=”自分” type=”r”]へぇ~。美味しかった?[/voice]
バックトラックを使った会話
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon02.jpg” name=”相手” type=”l”]昨日、スタバの新作飲んだんだ~[/voice]
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon.jpg” name=”自分” type=”r”]へぇ~。スタバの新作飲んだんだ~。美味しかった?[/voice]
バックトラックの種類
バックトラックには以下の五種類の方法があります。
これらはどれが良いというわけではなく、その場面に応じた適切な方法で返すことが大切です。
バックトラックの種類 A.相手の言葉から事実を送り返す |
A.相手の言葉から事実を送り返す
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon02.jpg” name=”相手” type=”l”]昨日、スタバの新作のメープルラテ飲んだんだ~。ちょー美味しかったよ[/voice]
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon.jpg” name=”自分” type=”r”]へぇ~。スタバの新作飲んだんだね[/voice]
B.相手の言葉から感情を送り返す
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon02.jpg” name=”相手” type=”l”]昨日、スタバの新作のメープルラテ飲んだんだ~。ちょー美味しかったよ[/voice]
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon.jpg” name=”自分” type=”r”]へぇ~。そんなに美味しかったんだね[/voice]
C.相手の言葉を要約して返す
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon02.jpg” name=”相手” type=”l”]昨日、スタバの新作のメープルラテ飲んだんだ~。ちょー美味しかったよ[/voice]
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon.jpg” name=”自分” type=”r”]へぇ~。新作のメープルラテがすごく美味しかったんだね[/voice]
D.相手の言葉を別の表現にして返す
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon02.jpg” name=”相手” type=”l”]昨日、スタバの新作のメープルラテ飲んだんだ~。ちょー美味しかったよ[/voice]
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon.jpg” name=”自分” type=”r”]へぇ~。さっそくスタバの新作を体験してきたんだね。しかも美味しくてよかったね[/voice]
E.相手の言葉に含まれる感情を相手の考え方や過去の事実を付け加えて返す(スーパーバックトラック※)
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon02.jpg” name=”相手” type=”l”]昨日、スタバの新作のメープルラテ飲んだんだ~。ちょー美味しかったよ[/voice]
[voice icon=”https://leyl-lovecourse.jp/wp-content/uploads/2018/06/icon.jpg” name=”自分” type=”r”]前から気になってるって言ってたもんね。やっと飲めてよかったね![/voice]
※スーパーバックトラック
性質上、相手のことをよく理解していなければ行うことができないが、相手にバックトラックされていると感じさせず、しかも相手の発言ではなく意図に理解を示すので、強い好感を得ることができる。恋愛上級者必須スキル。
キャリブレーション
ノンバーバルメッセージから相手の心理状態を読み取る
人は自分の気持ちを言葉だけでなく、表情や身振り手振り、声のトーンなど、様々な状態の変化によって表しています。
これらノンバーバルメッセージから相手の気持ちを読み取ることをキャリブレーションと言います。
たとえば、同僚の女性が急いで書類を運んでいて躓いてしまい床にばらまいてしまった時に拾うのを手伝ってあげた際、相手が嬉しそうな笑顔で「ありがとう」と言えば、「本当に喜んでくれている」と思いますよね。
それに対し、友達の誕生日に置時計をプレゼントした時、相手が「ありがとう」と言っていても、表情があまり嬉しくなさそうであれば、「この置時計はあまり好みじゃないんだろうな」と感じると思います。
このように、人は言葉以外でも自分の感情を表しているのですが、それを意識的に読み取るようにする方法がキャリブレーションです。
キャリブレーションを行う箇所 視線 声のトーン など |

アクセシングキュー
状態解析
相手が自分の心にアクセスした際に、それが表層に出る変化をアクセシングキューと言います。
たとえば、緊張している時は身体がこわばったり小刻みに震えたりしますが、こちらが相手を見た際に、相手が身体こわばらせたり小刻みに震えているのを見ることで緊張していることを読み取ることができます。
このように、相手の身体の変化から相手の心理状態を読み取ることをアクセシングキューと言い、有名なものには「アイ・アクセシング・キュー(視線解析)」があります。
アイ・アクセシング・キュー
アイアクセシングキューは、相手の視線の変化から相手の心理状態を読み取る方法です。
人は何かを考えたり、イメージしたりする時にも視線が動きます。
その際、アクセスしている感覚によって動きに特徴が見られるので、これによって相手の思考を推測したり、昨日の出来事を思い出す為に利用したりすることができます。
視線の方向とアクセスしている感覚 左上:未来のイメージ 右上:過去に見た映像 ※こちらから見た相手の目の方向。なお、左利きの人は左右が逆の場合がある。 |

たとえば、相手に「昨日、どんなテレビ番組見たの?」と聞くと、多くの場合※で相手の目は左上に動きます。 ※80%
これは、映像の記憶を思い出そうとしているからです。
また、昨日見たテレビ番組を思い出したいときは目を左上に動かすことで、思い出しやすくなると言われています。
これは左上に視線を向けることで脳が過去の映像にアクセスする手助けになるからです。
リフレーミング
視点切替
人は自分なりの世界観(地図)を通して世界を見ています。
この視点(フィルター)の事をフレームと言います。
そして、視点を切り替えて別の視点から物事を見ることをリフレーミングと言います。
自分に行うリフレーミング
どんなことでも捉え方次第で良くも悪くもなります
たとえば、「堅物」という人も言い換えれば「真面目」と言うことができます。
また、どんなことでも見方を変えることで、違うものが見えてきます。
たとえば、赤色を探している時は赤色の物しか気付きませんが、黒色のものを探せば黒色の物に気付くことができます。
同じように、相手に対して苦手意識があれば嫌な部分ばかりが目につきますが、良いところを探すようにすれば色々なことに気付くはずです。
相手に行うリフレーミング
目的にたどり着く為の手段は1つではありません。
より良い方法に気付かせてあげることができれば、そちらへと誘導することが可能となります。
たとえば、ストレスを解消したくてタバコを吸っている人に、「タバコを吸う理由(目的:ストレスの解消)」と「タバコの弊害(現在の手段の悪さ)」に気付かせてあげて、「ガムを噛むことの良さ(新しい手段とそれによる良い効果)」の提示を行うことで、タバコを吸うのをやめる方向へと誘導することができます。

メタモデル
相手から情報を正確に引き出す
メタモデルは相手の曖昧な表現を追求することで、相手の潜在意識を明確にします。
省略
※各技法におけるカテゴリは使い方によって変わったりするので目安としてお考え下さい
①不特定名詞(単純削除、指示詞の欠如)
不特定名詞一例
何が
何に
誰が
誰に
いつ
どこで
何を
何の
どんな
どのように
具体的に誰が?
具体的に何に?
不特定名詞例文
相手「困りました」(単純削除)
自分「何に困っているのですか?」
相手「みんなが言っています」(指示詞の欠如)
自分「みんなとは誰でしょうか?」
相手「よく開催されています」
自分「よくとはいつですか?」
相手「そのことを知ってもらいたいんです」
自分「そのこととは何のことですか?」
相手「買って下さる人もいます」
自分「どんな人ですか?」
「なぜ?」は使わないこと
人は「なぜ?」とだけ聞かれると、理由を求められていると感じるのですが、相手が「なぜ?」と聞いてくる=相手にとってこちらの理由は良くないと捉えていると感じる為、相手が納得できるであろう理由=言い訳を考えてしまう傾向があります。
たとえば、「なぜ、食べたのですか?」と聞かれると、食べた理由を相手が理解した上で聞いてくる=こちらの本心を答えると否定されると考える為、本心がお腹が空いていた場合は「食べる物が他になかったから」「机の上に置いてあったから食べてもいいと思った」などと答えて、本心である「お腹が空いていたから」とは答えません。
また、「なぜ?」と聞かれると、相手にとってこちらの理由は良くないと捉えている=怒っている、怒られている、責められているなどと感じてしまう為、相手に威圧感や嫌悪感を与えてしまいます。
相手と仲良くなる為にコミュニケーションを行うのであり、また相手の本心を知ることでコミュニケーションを円滑にすることができる為、「なぜ?」と言う聞き方はしないように気を付けましょう。
②不特定動詞
不特定動詞一例
どうして
どうやって
どんなふうに
どのように
具体的に言えば?
詳しく言えば?
不特定動詞例文
相手「困りました」
自分「どんな風に困っているのですか?」
相手「やっておいてください」
自分「何をどういうふうにすればいいですか?」
相手「困ってしまいます」
自分「どうして困ってしまうのですか?」
③名詞化
名詞化一例
具体的にどういったこと?
具体的にどのように○○するの?
名詞化例文
相手「彼はとても勉強ができるわ」
自分「何がどんなふうにどれくらいできますか?」「それが社会的に証明されるような事実はありますか?」
相手「仕事がとても大変です」
自分「何がどう大変ですか?」「具体的にどのように大変ですか?」
相手「頑張っているよ」
自分「何に向けて、どんな風に頑張っていますか?」「頑張ることでどうなりますか?」
④比較削除(比較)
比較削除一例
何と比べて
誰と比べて
何の中で
どの範囲で
比較削除例文
相手「私は鼻が低いです」
自分「誰と比べて低いのですか?」
相手「あの人はとてもわがままだよね」
自分「どれくらいわがままですか?」
相手「こっちの方が早いよ」
自分「何と比べて早いのですか?」
歪曲
⑤判断
判断一例
誰の判断なのか
どういった判断基準なのか
判断例文
相手「彼は先生として良くない」
自分「誰がそう思っているんですか?」
相手「あの人は素晴らしい感性を持っている」
自分「その素晴らしさは何を基準にしていますか?」
⑥複合等価(等価の複合観念)
本人が思い込みで勝手に等価にしている観念
複合等価一例
相手「A=B」
自分「何故、A=Bだと思うのか?」
複合等価例文
相手「彼から連絡がありません。彼から嫌われていると思います」
自分「連絡が無いということは、嫌われていることになるのですか?」
⑦前提
何かを前提とした発言
前提例文
相手「私にはできません」
自分「何故、できないと思うのですか?」
相手「失敗してしまいました」
自分「何をもって失敗したと思うのですか?」
相手「黄色よりも緑色がいいと思いますよ」
自分「まだ買うとは決めていないのですが」
⑧因果関係(因果)
原因に対する思い込み
因果関係例文
相手「さっき黒猫が横切ったから、今日は運が悪いと思います」
自分「何故、黒猫が横切ったら運が悪い言えるのですか?」
相手「上司のせいで仕事が上手くいきません」
自分「上司がどのようにしてあなたの仕事の邪魔をするのですか?」
⑨憶測(マインドリーディング)
他人に対する決めつけ
憶測例文
相手「あなたは嫌だと思っているのですよね?」
自分「どうしてそのように思うのですか?」
相手「部下が信頼してくれていません」
自分「どうしてそれがわかるのですか?」
相手「あの人に言っても理解してもらえないと思います」
自分「どうしてそう思うのですか?」
一般化
⑪可能性の叙法助動詞(可能性の様相記号)
本人が勝手に定めた限界
可能性の叙法助動詞一例
~できない
~することは不可能
可能性の叙法助動詞例文
相手「女性と会話をすることができません」
自分「どうしてできないと思うのですか?」「あなたの会話の定義は何ですか?」
相手「仕事が終わってから勉強をするなんて無理です」
自分「何故無理なのですか?」「たとえ5分だけでもすることはできないのですか?」
⑫必要性の叙法助動詞(必然性の様相記号)
本人が勝手に定めた行動
必要性の叙法助動詞一例
~しなければならない
~するべき
~してはいけない
~するべきではない
必要性の叙法助動詞例文
相手「私は友達との付き合いを我慢しなければならない」
自分「何故我慢しなければならないのですか?」「我慢しないとどうなりますか?」
相手「私は頑張ってダイエットするべきです」
自分「ダイエットしなければどうなりますか?」
⑬全称限定詞(普遍的数量詞)
本人が勝手に定めた基準や概念
全称限定詞例文
相手「いつも失敗してしまいます」
自分「これまでにただの1度も上手くいったことはないのですか?」
相手「外国人はフレンドリーです」
自分「例外なく全員がそうだと思いますか?」
ミルトンモデル
言葉を意図的に曖昧に使う
ミルトンモデルはあえて曖昧な表現を使うことで、相手が自分で好きな意味付けを行えるようにします。
メタモデルの逆バージョンとも言えます。
省略
①不特定名詞(単純削除、指示詞の欠如)
誰が、いつ、どこで、なにを、誰に、どうして、どのようになどを具体的に述べないことで、聞き手に自由に解釈させる方法です。
不特定名詞
誰が
いつ
どこで
なにを
誰に
どうして
どのように
不特定名詞一例
「私たちは」
「人は」
「いつか」
「いつでも」
「それ」
「そのこと」
②不特定動詞
変わる、学ぶ、思うなどのように抽象的な表現をし、具体的な内容を述べないことで、聞き手に自由に解釈させる方法です。
不特定動詞一例
「変わる」
「学ぶ」
「思う」
不特定動詞例文
「この3日であなたは大きく変わりました」
「たくさんのことを学べましたね」
「色々と思うところはあったのではないでしょうか?」
③名詞化
思考や行動のプロセスを名詞にすることで具体的な情報を省略し、聞き手に自由に解釈させる方法です。
名詞化例文
「あなたは素晴らしい可能性を秘めています」可能性
「あなたはその問題の解決方法を知っているはずです」問題、解決方法
「最高の体験ができるに違いません」体験
④基準の省略(比較削除、判断)
比較対象や基準を省略することで、聞き手に自由に解釈させる方法です。
基準の省略例文
「より良くする必要があります」(どのように?が省略されている)
「さらに美味しくなりました」(何に比べて?が省略されている)
歪曲
⑤複合等価(等価の複合観念)
前の事実と後ろの虚実が同等であるかのように思わせます。
複合等価一例
「~は、です」
「~なら、~です」
複合等価例文
「ここのメンバーは一流だけが集まる」
「このクラブの会員は一流の証明です」
「健康に気遣い始めたということは、身体が危険信号を発している証拠だよ」
⑥同時性の暗示(連結語)
前の言葉と後ろの言葉を繋げることで、因果関係があると思い込ませます。
同時性の暗示一例
そして~
~したら~、~すると~、~すれば~
同時性の暗示例文
「あなたは私の声を聴いています。そして、心がどんどんと穏やかになっていくのを感じています」
「早起きしたら、健康になれます」
「たくさんの友達を作ると、毎日が楽しくなります」
「このカメラを使えば、どんな景色も美しく撮れます」
⑦マインドリーディング(読心術)
相手の考えや気持ちがわかるかのように言うことで、強い関心や共感を引き出します。
わかっているかのように振る舞う方法と、得られる情報から予想する方法があります。
わかっているかのように振る舞う
「私がこれから話すことに、あなたはきっと興味があるはずです」
「もし私があなたの血液型を当てることができたらどうしますか?」
表情、会話の内容、状況、いきさつなどから予想する
「とても嬉しいですよね」
「それはとても悲しかったでしょう」
「自信を無くしてしまったのですね」
なお、あまり踏み込んで逆に的外れなことを言ってしまうと、相手の疑心を引き出してしまうので注意が必要です。
前提
⑧時の従属節
~の前に、~の間、~の後でなどの言葉を使うことで、相手に前提を認めさせる方法です。
時の従属一例
~する時
~の前に
~の間
~しながら
~の後で
時の従属節例文
「あなたが実践する前に注意しておくことがあります」
「女性がトイレに行っている間に支払いを済ませておきましょう」
「お祝いするのは就職先が決まった後にしましょう」
⑨序数(順序)
初めは~、次は~などの言葉を使うことで、相手に前提を認めさせる方法です。
序数一例
「初めは~」
「次は~」
「最後に~」
序数例文
「初めは算数にしますか?それとも国語にしますか?」
「初めは誰でも戸惑うものです」
「次にランニングを行うことが効果的です」
⑩「または、あるいは、さもなければ」(二者選択)
または、あるいは、さもなければ、それとも、もしくはなどの言葉を使うことで、相手に前提を認めさせる方法です。
「または、あるいは、さもなければ」一例
「または」
「あるいは」
「さもなければ」
「それとも」
「もしくは」
「または、あるいは、さもなければ」例文
「コーヒーにしますか?紅茶にしますか?」
「京都なんていいですね。または奈良でもかまいません」
「今週中にお願いできますか?あるいは来週までかかりますか?」
「掃除しておいてくれますか?それとも子供の面倒を見てくれますか?」
「契約にお伺いするのは平日または休日のどちらがご都合よろしいでしょうか?」
ダブルバインド(二重拘束)について
ダブルバインドを「二択によって前提を受け入れさせる方法」「選択肢の提示によって相手に意思決定をさせないテクニック」と説明してあるものを見かけますが、本来のダブルバインドは「二重拘束」という意味で、矛盾したコミュニケーションによって精神にストレスを受けている状態を指します。
ダブルバインド
どうしても悪い結果になってしまう指示のことであり、またそれを受けた状態のことです。
一例:上司が部下に指示を出し、必ずダメ出しをする
部下は指示を無視しても叱られ、指示に従ってもダメ出しされるので、どうしたらいいかわからなくなり、精神に支障をきたすようになる
なお、嫌悪感が対象に向くことになるので、悪い使い方をすれば嫌われます。
ダブルバインドに限らず、NLPの技術は必ず二人がハッピーになれる使い方をしましょう。
治療的ダブルバインド(エリクソニアンダブルバインド)
患者の治療を行う目的でミルトン・エリクソン氏が考案したダブルバインドです。
例文「こちらへ来たくなければそのまま話を聞いてもらってもいいですし、座りたくなったらこちらへ来て座って頂いてもかまいません」
例文「誰でも指摘されてから1週間以内に頭を掻くクセは直るってことをあなたはまだわかっていないようだ。だから、今日から1週間は頭を掻くことを意識せずに普通に過ごしなさい」
ポジティブダブルバインド
ポジティブな前提を受け入れさせることで、相手の心をポジティブに導く方法です。
例文「あなたには秘められた力があることに気付いていますか?」
誤前提暗示(ダブルバインドの一種)
治療的ダブルバインドの仕組みを利用して自分に都合の良い方向へと誘導する方法です。
二択によって前提を受け入れさせます。
恋愛テクニックとして使われている方法の多くはこれを指します。
例文「コーヒーにしますか?紅茶にしますか?」
例文「デートするなら遊園地と映画、どっちがいい?」
なお、「この方法を使えばどちらかを受け入れることになるから、必ず目的を達成することができる」と書いてある説明を見かけますが、そもそもとして仲良くなければ(ラポールを築けていなければ)
「デートするなら遊園地と映画、どっちがいい?」 → 「どっちも嫌」
「デートするなら遊園地と映画、どっちがいい?」 → 「どちらかと言えば映画かな?」 → 「それじゃ今週空いてる日に行こうよ」 → 「嫌」
と、断られることになりますし、この提案の仕方をして断られた場合、「前提がおかしい=頭がおかしいから関わらないようにしよう」「誘導しようとしてくるヤバい奴だから関わったら危険」などと思われて余計に嫌われてしまう為、安易に使うことはオススメできません。
ネガティブダブルバインド
ネガティブな前提を受け入れさせることで、相手を説教したりそれによって立場的に上に立つ方法です。
ただし、やりすぎると嫌われてしまったり、逆ギレされる恐れがあるので注意が必要です。
例文「あなたは誰かを傷付けているとわかってそれをやっているのですか?」
⑪意識の叙述語(気付きの叙述語)
気付いている、知っている、わかっているなどの言葉を使って質問することで、相手に前提を認めさせる方法です。
意識の叙述語一例
「気付いている」
「知っている」
「わかっている」
意識の叙述語例文
「あなたは自分でそれができるって気付いていますか?」
「私がそれの初心者であることを知っていましたか?」
「あの会社は怪しいということをわかっていますか?」
⑫副詞と形容詞
状態を示す言葉を使うことで、相手に前提を認めさせる方法です。
「あなたは仕事を始めることができますか?」焦点は仕事ができるかどうか
「あなたは早く仕事を始めることができますか?」仕事をすることは前提で、焦点は早く始めることができるかどうか
副詞と形容詞一例
「すぐに」
「早く」
「ゆっくり」
「簡単に」
「もっと」
「深く」
など
副詞と形容詞例文
「あなたは早く仕事を始めることができますか?」 ⇒ 仕事を始めることが前提
「あなたなら簡単に選ぶことができますよね」 ⇒ 選ぶことが前提
「あなたはもっと自分を成長させたいですか?」 ⇒ 成長していることが前提
⑬時の変化の動詞と副詞(時制と副詞の変更)
すでに、もう、まだ、始めた、終わった、続ける、やめるなどの時間の経過を表す言葉を使うことで、相手に前提として認めさせる方法です。
時制と副詞の変更一例
「すでに」
「もう」
「まだ」
「始めた」
「終わった」
「続ける」
「やめる」
など
時制と副詞の変更例文
「あなたが仕事を始めたのはいつですか?」
「あなたはもうその仕事を始めていますか?」
⑭論評的形容詞と副詞(注釈の形容詞と副詞)
幸いにも、幸運にも、運良く、偶然にも、必然的に、驚くことになどの評価を示す言葉を使うことで、その後に続く言葉を相手に前提として認めさせる方法です。
ただし、後に続く言葉が本当になるというわけではないので、嘘を本当にする為に使うようなことはできません。
論評的形容詞と副詞一例
「幸いにも」
「幸運にも」
「運良く」
「偶然にも」
「必然的に」
「驚くことに」
論評的形容詞と副詞例文
「幸運にも、私はどうすればこのプロジェクトが成功するかを知っています」
「驚くことに、この車は行く先々で感動を生み出してくれます」
一般化
⑮全称限定詞(普遍的数量詞)
全部、いつも、どんな~でも、みんな、必ずになどの言葉を使うことで、その後に続く言葉を相手に認めさせる方法です。
「あなたの話は面白いです」
「あなたの話はいつも面白いです」
「この商品は良いと思います」
「この商品は良いとみんなが言っています」
全称限定詞一例
「全部」
「すべて」
「あらゆる」
「いつも」
「いつでも」
「常に」
「~するたびに」
「ふつう」
「どんな~でも」
「誰でも」
「みんな」
「必ず」
「絶対に」
「決して」
全称限定詞例文
「ふつうは就職する前に面接を行います」
「無職はふつうではありません」
「いつも非常事態に備えておくべきです」
「このお店ではいつも洋楽がかかっています」
「どんな家族でも、特別な想い出の1つや2つはあるもんさ」
⑯可能性の叙法助動詞(可能性の様相記号)
可能性の叙法助動詞一例
~できる
~することは可能
可能性の叙法助動詞例文
「あなたは女性と話せるようになることができます」
「私たちは経験によって成長していくことができます」
⑰必要性の叙法助動詞(必然性の様相記号)
できない、してはいけない、しなければならない、するべきであるなどの言葉を使うことで、その後に続く言葉を相手に認めさせる方法です。
必要性の叙法助動詞一例
~しなければならない
~するべき
~してはいけない
~するべきではない
必要性の叙法助動詞例文
「この問題を解決する為にも、前向きに検討するべきです」
「運転の際は、よそ見をするべきではありません」
間接的な誘導
⑱埋め込まれた命令(挿入命令)
相手に気付かれないように発言の中に命令や指示を伝える方法です。
埋め込まれた命令例文
「例の仕事を提出するのは今月中ならいつでもかまわないからね」
「もう少しだけ左に寄ることはできますか?」
「あなたはこの仕事に興味ありますか?」
「午前中に仕事を終わらせると気持ちがいいですよね」
「あなたがいつドコモに変えるのかは自由ですが、今月中だと割引きが効いてお得ですよ」
「あなたがドコモに乗り換えれば、毎月の高い使用料や電波が届かないといったストレスから解放されることができます」
⑲アナログ・マーキング
非言語情報によって言語情報の印象を強く残す方法です。
たとえば、キーワードだけ少しゆっくりめに大きく話す、声のトーンや口調を変える、軽くうなずく、手を動かしてジェスチャーをするなどです。
わかりやすい一例としては、「ダイエット、一緒に頑張りましょう!」と言う際に、「頑張りましょう」のところで声のボリュームを上げたり、ガッツポーズをしたりすることで、「頑張る」の印象を強くすることができます。
⑳埋め込まれた質問(質問挿入)
気になります、思いますなどの言葉を使うことで、相手に気付かれないように発言の中に質問を埋め込む方法です。
埋め込まれた質問一例
「気になります」
「思います」
埋め込まれた質問例文
「あなたがどんな仕事をしたいのかが気になります」
「この問題を解決できる方法を知ってる人がいたらいいんだけど」
21否定命令(否定的命令)
~しないでくださいと言う言葉を使うことで、相手にそれを想像させたり意識させる方法です。
たとえば「リンゴを想像しないでください」と言うことで、聞き手はリンゴを想像してしまいます。
また、「この本には絶対に触らないで下さい」と言うことで、聞き手は本を意識してしまいます。
22会話的要求(会話調の要請)
相手にしてほしいことを命令形ではなく質問系で伝えることで、相手が要求を受け入れやすくする方法です。
「こちらに座って頂けますか?」
「明日までに提出してもらえますか?」
さらに高度な方法として、YESの場合に行動を起こすように誘導する方法もあります。
「自分の血液型を言えますか?」
「ボールペンを用意できますか?」
23曖昧
言語表現を曖昧にして聞き手に自由に解釈させることで、聞き手は自分にとって最適な意味合いだと信じやすくさせる方法です。
音声的曖昧:2つ以上の意味を持つ言葉を使うことでイメージを与える
「日本でも有数の会社の社員である私たちは、自分たちの仕事に誇りを持ち、太陽のように光り輝くシャインとなりましょう」
シャイン:社員、shine
「悩みを自分に引き寄せないで、私にハナシテ下さい」
ハナシテ:放して、話して
範囲的曖昧:句読点の位置がはっきりしない言い回しで自由に解釈させる
「これから恋愛を学んでいくあなたは素敵な彼女を作ることができるでしょう」
「これから恋愛を学んでいくあなた」「あなたは素敵な彼女を作ることができる」のように、あなたが2つの言葉にかかっています。
「とても効果の高いA製品とB製品はよく売れています」
「とても効果の高いA製品」と「B製品」なのか、「とても効果の高いA製品&B製品」なのかが曖昧になっています。
構文的曖昧:曖昧な言い回しで2種類の意味から好きな方を選択させる
「高い才能を発揮させる恋愛講師」
恋愛講師自身が才能を発揮させるのか、生徒の才能を発揮させるのか
「すぐに終わらせることができる問題が発生した」
その問題がすぐに終わらせることができるのか、すぐに終わらせることができてしまうことが問題なのか
メタファー(たとえ話)
24比喩
人や物の特徴を別のなにかにたとえて表現する方法です。
比喩一例
硬い:石頭
柔らかい:マシュマロのようなクッション
綺麗:宝石のようなお弁当
赤い:太陽のようなドレス
大きい+強そう:熊のような男
速い+一直線:レーザーのような投球
限界、制限:壁
「私の彼女無し人生にもようやく春が訪れた」
「恋愛はビジネスに似ている。WIN-WINの関係を築くことこそが成功の秘訣だ」
五感を使った比喩
視覚:「明るい未来が見える」「暗い過去」「輝ける人生」「黄色い声援」「腹黒い男」
聴覚:「腕が鳴る」「勝利のファンファーレが聴こえる」
嗅覚:「臭い話」「あいつの行動は何か臭う」
味覚:「美味しい話」「甘いハネムーン」「辛口の評価」「苦い体験」
触覚:「熱い想い」「冷たい視線」「心が痛い」
感覚:「よみがえる想い出」「あっと言う間」
隠喩、複合隠喩
「人生はオーケストラだ。様々な音が合わさるほど、深く豊かになっていく。あなたはこれからどんな音楽を奏でるのだろうか?」
「悲しみに濡れる君に、そっと傘を差したい」
25現実性の違反(事実違反)
本来はありえない表現の仕方をすることで、聞き手にイメージをさせる方法です。
主に何かを擬人化してたとえることが多いです。
現実性の違反一例
「今にも泣き出しそうな空」
「鰹節が踊っている」
「テレビも空気を読んでるね」
「俺のトークで地球を笑わせてしまったか…」
26引用
他人の言葉を利用することで、言葉に重みを持たせる方法です。
たとえば、ふてくされてやる気のない人に対して「頑張ってみましょう」と言うよりも、「ヘレンケラーの言葉を知っていますか?『人生はどちらかです。勇気をもって挑むか、棒にふるか。』あなたはどちらですか?」と言った方がやる気は促されやすくなります。
歴史上の名言や格言、ことわざや四文字熟語などだけでなく、相手が好きな人物や尊敬している人物であれば、芸能人やスポーツ選手、上司や祖父母でも言葉でも効果的です。
男性向けの格言一例
「人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにする為には、走り続けなければならない」アインシュタイン(ドイツ生まれの科学者)
「天才とは、努力する凡才のことである」アインシュタイン(ドイツ生まれの科学者)
「努力が効果を表すまでには時間がかかる。多くの人はそれまでに飽き、迷い、挫折する」ヘンリーフォード(アメリカの自動車メーカーの創設者)
「簡単すぎる人生に、生きる価値などない」ソクラテス(古代ギリシャの哲学者)
「ストライクが来るたびに、僕は次のホームランに近付く」ベーブ・ルース(アメリカの野球選手)
「誰にもノックされないなら、新しいドアを作ろう」ミルトン・バール(アメリカの俳優)
※ヤバいくらいに使える女性向けの格言一例や女性のマインドを変えて惚れさせてしまうNLPについてはこの記事の最後をお読みください。
四字熟語一例
因果応報
一生懸命
ことわざ一例
「石の上にも三年」
「善は急げ」
27物語
神話、伝説、昔話、おとぎ話、民話、寓話、逸話、体験談などの物語を利用することで、より強く印象付ける方法です。
たとえば、子供に対して誠実に生きることが大切だと伝えたい場合、「誠実に生きることが大切」と直接的に言うよりも「はなさかじいさん」を聞かせてあげた方が伝わりやすいと言えます。
物語はイメージとして心に残りやすく、長期的に影響を与えることができます。
また、イメージによって疑似体験することで説得力が増すので、体験談を語ることは非常に効果的です。
アンカリング
動作と感情の関連付け
アンカリングは五感から入力する特定の情報をトリガーとして、それに関連付けした感情や反応を引き起こす方法です。
たとえば、何かを見た時、聴いた時、嗅いだ時、味わった時、触った時に何かを思い出したり、特定の感情が呼び起こされることがあると思いますが、それがアンカー(錨)がかかった状態です。
人生経験において自然に作成されるアンカーにはポジティブなものとネガティブなものがありますが、意図的にポジティブなものを作ることで、集中したい時やスポーツで力を発揮したいときなどに役立てることができます。
アンカリングの種類
リソース・アンカー
スタッキング・アンカー
スライディング・アンカー
チェイニング・アンカー
スペーシアル・アンカー(空間アンカー)
コラプシング・アンカー
リソース・アンカリング
リソースアンカリングとは、自分自身の中にあるリソース(資源)とポーズやジェスチャーをアンカリングして、好きな時に呼び起こす方法です。
たとえば、イチロー選手のバッティング時の決まった動作や五郎丸選手の指ポーズなどは、集中力を高めて打席に臨む為のリソースアンカリングです。
このように、リソースアンカリングを活用すれば好きな時に好きな状態を作ることができるようになります。
リソース・アンカリングの作成手順
①アンカリングの方法を決める
まずはアンカリングの方法(動作)を決めましょう。
指パッチンや忍者の印、ガッツポーズや空手の押忍でもいいですし、
イチローや五郎丸のルーティン、
ハガレンのエドの錬金の時の合掌や
悟空の瞬間移動の際の頭に指を添えて瞑想する、
ファブルの集中モードに入る際の上向き頭トントンなどのように、
状態に入る時の方法を1つ考えましょう。
②状態を決める
次になりたい状態を決めましょう。
たとえば、
勉強や仕事で使いたい ⇒ 集中している状態
遊びやデートで使いたい ⇒ 元気がある状態
嫌なことがあった時に使いたい ⇒ 落ち着いている状態
役者の演技で使いたい ⇒ そのキャラクターになりきっている状態
などです。
余談ですが、昔、10秒以内に泣けたら100万円というテレビ番組の企画がありましたが、アンカリングで悲しい状態を作れば可能ですね。
③状態を作る
先ほど決めた状態の中で動作と結び付けていくので、まずは決めた状態を作りましょう。
たとえば、集中している状態のアンカリングを作りたいのであれば、まずは集中している状態を作り、ピークの直前で先ほど決めた動作を行うことで、集中の直前と動作がアンカリングされます。
決めた状態を作る2種類の方法:集中力を高める場合の例
A.その状態になることをする
自分の集中力が高まることをしましょう。
たとえば、ペンを立てる、ジェンガをする、トランプタワーを作る、早押しをする、脳トレする際などは集中力が高まりますので、これらを実践して集中力を高めます。
B.その状態を思い出す
自分が集中している時を思い出して脳内でイメージし、その状態に浸って集中力を高めていきます。
その際、目は開けていても閉じていてもどちらでもかまいません。
④ピークの直前でアンカリング
状態を作り、ピークの直前まで高まったら、直前で動作を行います。
たとえば「集中力が高まった状態」と「指パッチン」をアンカリングしたい場合は、集中力がピークになる直前で指パッチンを行います。
なお、指パッチンは日常でも比較的起こりやすい動作になる為、アンカリングされにくく、乱発してしまう恐れもある為、指パッチンをアンカリングする際は特殊な動作も付与することが有効です。
たとえば、ハガレンの大佐のように手を身体の近くにもっていき、指を鳴らしながら手を前に出すなどです。
⑤ブレイクステイト
心を一旦散らしてから落ち着き、フラットな状態に戻ります。
身体を動かしたりすることでブレイクステイトできます。
⑥アンカリングされるまで繰り返す
ブレイクステイトを行ったら、状態と動作がアンカリングされるまで③~⑤を繰り返します。
アンカリングされたら、後は動作を行うだけで状態に入ることができるようになります。
なお、③Aを毎回同じ方法で行った場合、そのイメージが定着してしまう為、イメージをフラットにする為にも色々な方法にするか、一度感覚を掴んだら次からはBにして感覚だけを掴むようにしましょう。
リソース・アンカリングの際の2つのポイント
①タイミング
アンカーは、その時の感情が強いほど強くかかりやすくなるという特徴があるので、意図的にアンカリングを行う際は強い感情体験のタイミングで行うことが効果的です。
また、もし感情強度が強くない場合でも、繰り返しアンカリングを行うことでアンカーがかかりやすくなります。
②形
リソースアンカリングをいつでも使えるようにする為には、特定の動作やポーズを決めておく必要がありますが、普段から行うような動作やポーズであればアンカーの効き目が弱くなってしまいますので、普段しないような動作やポーズを設定する必要があります。
しかし、かと言ってあまりに難しい動作や人前で行うのに恥ずかしい動作などにすると、使いたいときに使えなくなってしまいますので、ある程度の特殊さを持ちつつも正確に5秒以内に再現できる動作にしましょう。

チャンクアップとチャンクダウン
チャンクとは状況や現象をどれくらいの規模で捉えるかを表す言葉で、
全体を俯瞰してみようとするのがチャンクアップ、
詳細を細かく確認しようとするのがチャンクダウン、
同じ高さで物の見方や伝え方を変えるのが水平チャンクです。
たとえば、あなたが友達をタイ旅行に誘いたいとします。
Aくんはそもそも旅行自体があまり好きじゃなくて旅行の何がいいのかよくわかっていません。
その場合は旅行することで世界観が変わるなど、旅行をすることの良さを教えてあげる必要があります。
これがチャンクアップです。
それに対しBくんはタイ旅行するなら予算がどれくらいかかって、旅先でどんなことをするのかを気にしています。
その場合はタイに行くのにどれくらいの時間がかかって、何日くらい滞在して、費用はどれくらいかかって、タイのどこの都市に行って、どんなことをするのかを詳しく説明してあげる必要があります。
これがチャンクダウンです。
相手が細かいことを気にするタイプなら、こちらがおおざっぱに伝えようとしても伝わらないので、その場合はメタモデルを使って詳細を明確にしてあげることが有効です。
逆に相手がおおざっぱなタイプなら、こちらが細かく説明しようとすると面倒臭くなってしまうので、その場合はミルトンモデルを使って相手に合わせてあげることが有効です。
また、相手が細かいことを気にするタイプで相手の視点を大きくしたい場合は、まずは自分がチャンクダウンして相手の視点に合わせ、ラポールを築いてからミルトンモデルを使って相手の視点を上げてあげることで、相手の視点を大きくすることができます。
それに対し、逆に相手がおおざっぱなタイプで相手の視点を細かくしたい場合は、まずは自分がチャンクアップして相手の視点に合わせ、ラポールを築いてからメタモデルを使って相手の視点を下げてあげることで、相手の視点を細かくすることができます。
なお、同じ高さなのに伝わらない場合は、メタファーを使って現在の状況を言い換えてあげることで、より伝わりやすくすることが可能になります。
チャンク一覧 チャンクアップ ⇔ ミルトンモデル |
サブモダリティ
五感要素
サブモダリティは五感における要素のことです。
サブモダリティの要素一例 視覚:色、形、明るさ、大きさ、動き、距離、位置など |
人は五感から得られる情報と記憶を関連付けて覚えています。
裏を返せば、サブモダリティを変化させることで記憶や気持ちを変えることができます。
これをサブモダリティーチェンジと言います。
これによって現状から受けるイメージを変化させることが可能になります。
苦手を克服する
あなたが苦手だと思うものを想像してみてください。
次に、そのイメージを変化させてみてください。
たとえば、対象を小さくしてみたり、色を変えてみたり、対象が人間なら喋り声を変な声にしてみたり(笑)
そうすることで、苦手意識が薄らぐと思います。
良い状態をさらに良くする
気分が良い状態を思い出してみてください。
たとえば、南国にバカンスに行っている自分とか、自室でくつろいで好きな音楽を聴いている状態とか。
次にそのイメージのうち、自分の気持ちを良くしてくれている要素をさらに良くしてみます。
南国でバカンスなら空や海の色をさらに綺麗にしてみたり、好きな音楽を聴いているなら音をよりクリアにしてボリュームを少し上げるような感じです。
そうすることで、さらに気持ちが上がってくると思います。
クリティカルボイス
クリティカルボイスとは、自分の中で自分を批判する声のことです。
何かに失敗した時に「なんて自分はダメなヤツなんだ」と、自分で自分を責めてしまう人がいると思います。
その言葉には肯定的意図が含まれていることが多いのですが、精神的な辛さで肯定的意図に気付くことが難しくなってしまっています。
そんな場合に、その声を小さくしてみたり、変な声にしてみたりすることで嫌な気持ちを無くし、その声のいい部分(肯定的意図)だけを受け取れるようにすることが大切です。

モデリング
モデリングとは、モデルとなる人物の思考パターン、行動パターン、考え方、話し方、見た目、動作、クセなどを分析して真似をすることで、その人と同じような結果を得ることができるようになる方法です。
たとえば、あなたが全くモテないとします。
その場合はモテる男性を見つけて、その人の考え方、思考パターンや行動パターン、しぐさやクセをマネし、成功体験を体感します。
そうすると、これまでは女性と接する時にどうしていいかわからなかったような場面であっても、自然と正解の行動がわかるようになり、相手に好かれることができるようになるのです。
これをモデリングと言います。
モデリングのポイント
①理想の相手を決める
人はそれぞれ考え方は違うので、複数の人物を同時にモデリングすることはできません。
そこで、まずはモデリングのモデルとする人を1人決める必要があります。
これは自分が理想とする理想像に近い人や、根底にある信念が同じような人が望ましいと言えます。
②徹底的に観察する
その人がどういう思考をし、どういう行動をしているかを知るために、普段の行動を徹底的に観察する必要があります。
その人と仲良くなって一緒に行動することが理想的ですが、それができない場合はできるだけ情報を集めます。
生活パターン:何時に起きて一日何をして過ごしているのか?何故そうしているのか?
生活の拠点:どこに住んでいるのか?どんなところに住んでいるのか?なぜそこに住んでいるのか?
生活用品:どんなものを使っているのか?どういうふうに使っているのか?何故それを使っているのか?
外見:どんな髪型や服装をしているのか?どういった手入れを行っているのか?どういう部分に気を使っているのか?
対人関係:どんな人と付き合いをしているのか?どういうふうに付き合いをしているのか?
コミュニケーション:どういう話し方をするのか?
③マネする
可能な限りそれをマネするようにします。
たとえば、喋り方や表情の作り方、着ている服のブランドや服装、普段の行動パターンや女性との接し方などです。
マネをすればするほどその人の成功マインドが身に付くようになり、結果を出せるようになってくるでしょう。

真のNLP
相手とラポールを築き、メタモデルによって相手の発言の真意を明確にし、ミルトンモデルでこちらの伝えたいことと相手の気持ちを一致させる。
と、ここまでが一般的に知られているNLPの使い方です。
ですが、実はこれはNLPの真の姿ではありません。
真のNLPは、催眠と誘導にあります。
メタモデルは単に質問によって相手の真意を明確にする為の技法ではなく、質問によって相手の思考を誘導するように使うことができます。
ミルトンモデルはやんわり伝える方法ではなく、相手の無意識に働きかけて行動をコントロールする方法です。
・埋め込まれた命令の違い
一般的なNLP「コーヒーでも飲みたい気分だよね」
⇒ こちらがコーヒーを飲みたいと思っていることが柔らかく伝わる
真のNLP「ちょっと疲れたね。こんな時、コーヒーでも↓あるとまた頑張れそうだよね」
(相手が疲れを感じたタイミングで話しかける、赤字は相手の目を見ながらボリューム1.1倍で話す、↓は語尾を下げる)
⇒ 相手がコーヒーを飲みたい気持ちになる
しかしながら、これらの技法は非常に強力で相手の人生を左右しかねない為、善意の無い者に知られるわけにはいきませんでした。
だから、簡略化された方法だけが広く知られるようになったのです。
NLPer(ネルパー。エヌエルピアーとも。NLPを学び実践する人)でも、この事実を知っている人は多くありません。
日本NLP協会でも、NLPプラクティショナー認定コース(379,000)を修了した後のNLPマスタープラクティショナー認定コース(398,000)でしか教えていません。
レイルでも、マスターコース受講者にしかこの方法は教えていません。
なぜなら、「相手を幸せにする」という人格の土台を作った後でなければ、危険すぎて教えることはできないからです。
そしてその土台は、自分の成長に対して投資できるだけの覚悟を持つ人でなければ作ることはできません。
向上心の低い人は安さや無料にこだわり、それでいて何かあれば自分ではなく他人が間違っていると考えます。
だから成長することはできませんし、人に好かれることもできません。
それに対して向上心の高い人は文句や不満を言ったりせず、何かあれば自分の落ち度を探して改善することができます。
だから成長することができますし、素晴らしい人格が作られていくのです。
もちろんのこと、それは1日や2日で作れるようなものではありません。
それらの事実を踏まえて、日本NLP協会もレイルも、ハードルを高くしつつ教育の日数を確保しているのです。
他人の人生を左右するほど強力なコミュニケーションスキルであるNLPの真の姿。
失敗しても他人のせいにしたりせず、「自分の人生を素晴らしいものにしたい」という意思のある人だけが、この最強のコミュニケーションスキルを学ぶ資格があるのです。